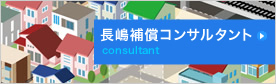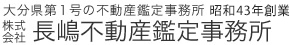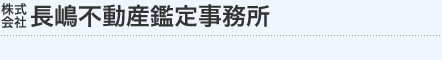家族信託という選択(4)
2020年8月11日
【家族信託を利用した数次相続対策の例】
家族信託を利用することによって、1次相続だけではなく、2次・3次相続まで自分の財産を意中の後継者に引き継ぐことが可能になります。
1.相談内容
A(相談者・65才)と妻B(63才)との間には、子どもがいない。Aの両親は既に他界しており、弟C(62才)がいます。この場合、Aが死亡した場合の法定相続分はBが4分の3、Cが4分の1です。
Aは、親から相続した不動産(自宅、アパート)を所有しており、Bが生きている間はBの利用を認めたいが、最終的にAの不動産を弟Cの子D(甥)(34才)に渡したいと思っています。
2.何もしなかった場合
認知症などでAの判断能力が喪失した場合には、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等の相続対策をすることができなくなります。また、Aの相続発生後、遺言を作っていない場合には、相続税申告期限内(相続開始後10か月以内)に法定相続人間で誰が何を相続するかを遺産分割協議でまとめる必要があり、相続争いが発生するリスクがあります。 また、遺産分割により、Aの不動産がBの所有となると、Bに相続が発生すればその不動産はBの親族に渡ってしまい、Aの意思に反することになります。
3.後見制度を使った場合
認知症などでAの判断能力が喪失した場合、Aに資産があるため、通常、親族は成年後見人になれず、弁護士、司法書士等の専門家が成年後見人になります。この場合、不動産の現状維持ための支出しか認めらなくなる可能性が高く、柔軟な財産管理ができなくなります。例えば、アバー卜の建替え、大規模修繕、売却等をすることができなくなる可能性が極めて高くなります。また、成年後見人に支払う費用(少なくとも月2万円以上)も必要となります。それに加え、妻Bの生活費などは、成年後見人と裁判所との協議が必要となり、柔軟な財産 管理ができなくなります。
任意後見制度を利用し、妻Bが任意後見人になったとしても任意後見の発効後、任意後見監督人が選任されるので柔軟な財産管理ができなくなります。
4.遺言を使った場合
夫婦A・Bで互いに遺言を書き合い、A亡き後はB、B亡き後はDというように財産承継先を指定することができます。但し、遺言はいつでも撤回できるため、将来、BとDの家族の関係が悪化した場合などは、撤回される可能性もあります。また、遺言には生前の財産管理機能がないため、認知症対策にはなりません。
5.家族信託を使った場合
A(相談者)を委託者、C(弟)を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利はAとするため受益者はAとする信託契約を締結します。そして、A亡き後はB、B亡き後はDというように財産承継先を指定することによって、Aの意思を反映した円滑な遺産相続が可能となります。
(こちらとほぼ同様の内容はOITA CITY PRESS 2020年8月号に掲載されています)
キーワード: